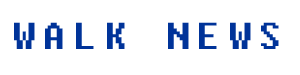琉球大学在学中の2024年、デビュー作『月ぬ走いや、馬ぬ走い(ちちぬはいや、うんまぬはい)』で群像新人文学賞と野間文芸新人賞をダブル受賞し、一躍注目をあつめた新人作家・豊永浩平。
このたび1年半ぶりに刊行された新作『はくしむるち』(講談社)は、現代の沖縄に生きる少年少女と、80年前の戦争に動員された少年兵たちの時空を交差させながら、時代を越えて繰り返される暴力の歴史と、それに抵抗する少年たちの「戦い」を描いた長篇青春小説です。
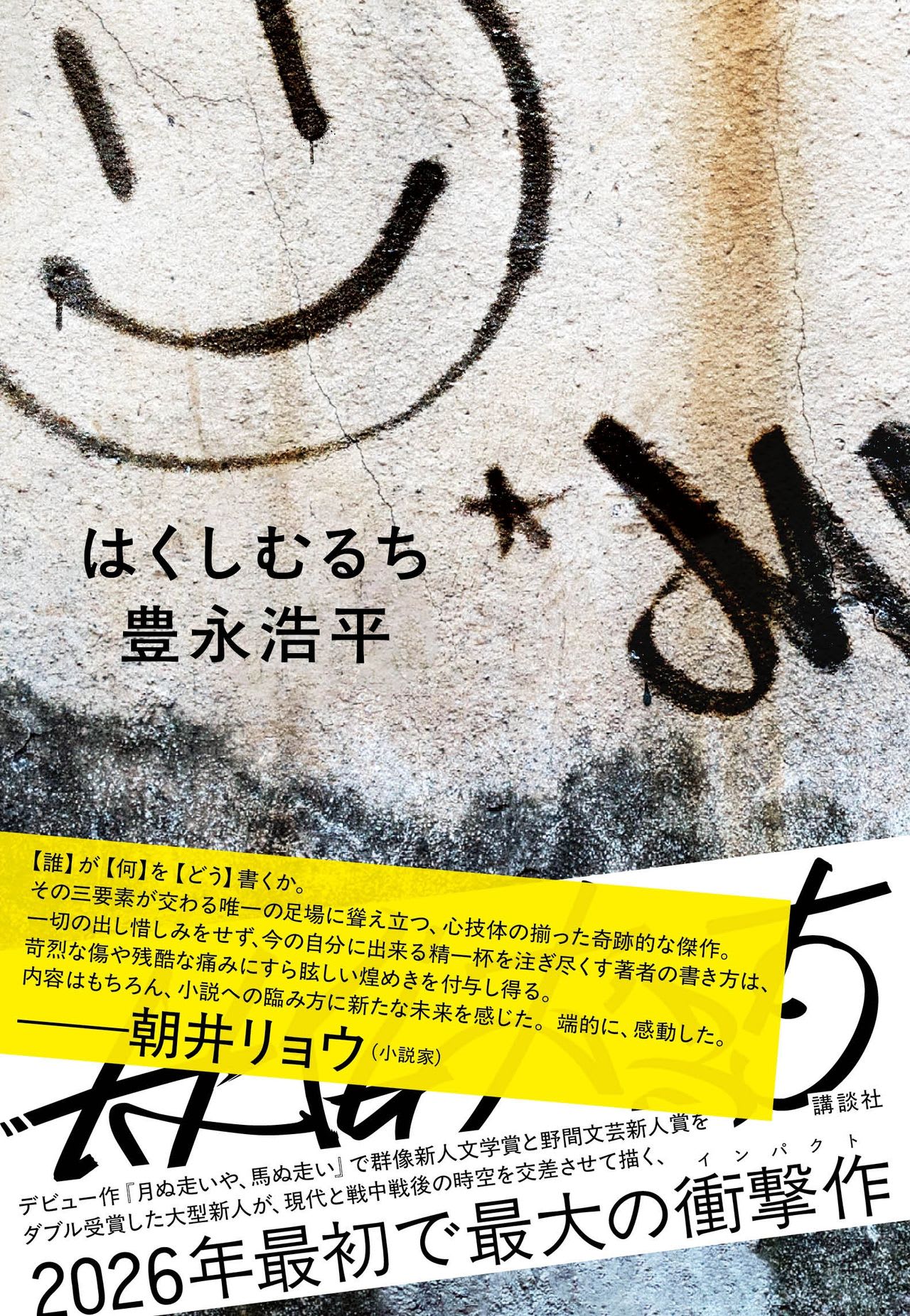 『はくしむるち』豊永浩平
『はくしむるち』豊永浩平
本書の刊行を記念して、作家・詩人の池澤夏樹さんとの初対談を、「群像」2026年3月号より転載して公開します。
沖縄と暴力の歴史
池澤 『はくしむるち』の刊行、おめでとうございます。
豊永 ありがとうございます。
池澤 よくこれだけ大きなことを企てて、実行なさったと感心しました。歴史を小説にするにはいろんなやり方があるけれど、豊永さんは沖縄という土地の歴史を、沖縄自身が沖縄を見る形で書いている。何人かの個人の生き方と運命を通して沖縄の戦後史を丸ごと描くという、その企ては成功していると思います。
沖縄は日本の中でも特別な土地です。琉球王国以来の歴史も、戦後の八十年の歴史も、日本の他の都道府県とは全く違う。何が違うかと言えば、暴力性です。振り返ってみれば沖縄の人たちは、ずっと暴力に苦しめられて生きてきた。もちろん楽しいこともいろいろあるけれど、基本的に沖縄に生まれて育つということは、暴力の受難の原理を押しつけられることだった。
最大の暴力は何かといえば、もちろん戦争です。戦争という国家単位の巨大な暴力があり、それが大きなものから小さなものまで形を変えて沖縄の現実に浸透して、最後は本作でも描かれた、学校の教室での「いじめ」にまでつながる。これは全て同じ暴力のトリクル・ダウンなんです。豊永さんはそれを異なる世代の、それぞれの個人の人生のある時期に焦点を当てて具体的に書いていく。そうやって歴史の縦糸と個人の横糸で織られた織物に、いろんな切実な感情を織り込んで、最終的に沖縄とは何か、どういう運命を負わされてきた場所であるか、その苦しさと痛みと悲しみを見事に表現していると思いました。
 池澤夏樹さん(撮影 森清)
池澤夏樹さん(撮影 森清)
豊永 そのように読んでいただけて光栄です。
池澤 小説の時系列をたどると、まず、主人公の大伯父である修仁(しゅうじ)と、戦争中の勤皇隊の少年たちの時代がある。一九四四年の沖縄大空襲直前から四五年の話ですね。彼らの多くは戦争で死んでしまうのですが、その運命をたどっていく。次は沖縄の日本復帰(一九七二年)前後の時代で、ベースタクシーの運転手をしている修仁の視点で占領下の沖縄が描かれる。それから今の時代になって、主人公の行生(ゆきお)と、友だちの瑞人(みずと)、円鹿(まどか)の三人を中心に、その周囲に集まった少年少女たちの過酷な、しかしそれぞれに達成感のある日々を、実に生き生きと書き上げて、大きな一枚の織物にしている。
前作の『月ぬ走いや、馬ぬ走い』では次々といろんなものを詰め込んで、ちょっと急いている印象もあったけど、今回の『はくしむるち』は場面場面に広がりがあって、ゆったりと読むことができました。
豊永 前作では沖縄の戦後八十年間を、どうにかまとめるのに精一杯でした。
 『月ぬ走いや、馬ぬ走い』豊永浩平
『月ぬ走いや、馬ぬ走い』豊永浩平
池澤 とはいえ今回も時代や人間関係が入り組んでいるので、次々とメモをとりながら読んだのですが、そうやって読み解いていくのはとてもおもしろかった。戦争中から現代まで長い時間が流れていく中で、最初から最後までずっといるのが大伯父の修仁ですね。
この修仁の立場というのは、『百年の孤独』におけるウルスラと同じなんです。全ストーリーを通じてその場にいて、すべてを見て、きちんと物事を考えて動いていく、読者にとって信頼できるキャラクター。その修仁の姪の子である行生と、同い年の円鹿と瑞人は、それぞれちょっと特別な才能を持っている。彼らは過酷ないじめや暴力を受けるけれど、その才能によって何とか苦難をしのいで、人生の中で何かをつかんでいく。
特に行生がグラフィティを描く場面がすばらしい。彼は絵の才能をグラフィティという形で発揮して、米軍基地の壁に落書きすることで、抵抗の道具にするわけですね。そうやって自分の才能をつかんで、自分なりの思想の表現としてグラフィティを描くというのはなかなかない発想で、バンクシーを連想させます。
一方で円鹿のほうは、沖縄の伝統芸能である組踊の「孝行の巻」をおどる場面で、その本質が「人身御供(ひとみごくう)」だとつかむ。そこで本作全体の大きなメッセージとして、沖縄がずっと人身御供だということが見えてくる。この二人の少年少女が作者によって特に祝福された登場人物で、その間に、トリックスターとして全体をつなぐ瑞人がいる。彼は沖縄の闇の中に引き込まれて辛い目に遭うけれど、愛すべきパーソナリティーです。読んでいくと細かい魅力は切りがなくて、いくらでもゆんたく(おしゃべり)できる小説ですね。
方言をどこまで使うか
池澤 その上で僕が、ここまでやるかと思ったのは、「うちなーぐち(沖縄語)」の使い方です。沖縄人(うちなーんちゅ)の読者や、沖縄に長く暮らした人はわかるけど、大和(やまと)の人たちには間違いなく読みづらいだろう。それでも沖縄語(うちなーぐち)でなければ本当の沖縄は書けない、そのくらい沖縄と言葉は強固につながっているという意図だと思いますが、ここまで貫くのは勇気が要りますね。
豊永 自分は小説にかなり沖縄語(うちなーぐち)を入れていくタイプで、『月ぬ走いや、馬ぬ走い』も沖縄方言の「黄金言葉(くがにくとぅば)」だし、『はくしむるち』の「むるち」は、沖縄語で「もどき」の意味です。基本的にネイティブの人の話し言葉は沖縄語をメインに考えて、分かりづらいところはルビを振りました。
池澤 方言を文学の中でどう使うかには、いろんなレベルがあって、例えば石牟礼道子は『苦海浄土』の中で水俣の言葉を使うけれども、直後に共通語の説明を盛り込んで、要所で効果的に生かしている。水俣の動詞で「されく」という言葉があります。うろつく、ほっつき歩くといった意味ですが、「これは高漂浪(たかざれき)のひっついた子じゃ」と言って、そういう魂を持っている子だと表現したりする。
特に方言が効果的なのは、感情表現のときですね。目取真俊(めどるま・しゅん)は「水滴」の中で会話の部分だけ沖縄語にしています。例を挙げれば主人公の徳正が戦争の時のことを語り部として話すことに批判的な妻のウシがこう言う─「噓物(ゆくしむぬ)言いして戦場(いくさば)の哀れ事語てぃ錢儲(じんもう)けしよって、今に罰被るよ」と書く。僕自身も沖縄を舞台にした『カデナ』という小説の中で、沖縄語を要所にはめ込んでトーンを高めました。だけど豊永さんの場合は、いわば文体全部を沖縄語まじりの日本語である「沖縄日本語(うちなーやまとぐち)」で通してしまった。僕は感心しましたが、どう読まれるか、ちょっと楽しみですね。
 『カデナ』池澤夏樹
『カデナ』池澤夏樹
豊永 僕が小説を考えるときに出てくるのは、まず言葉なんです。最初に沖縄語(うちなーぐち)と大和口(やまとぐち)をつなぐイメージで構成して、言葉で全体を引っ張っていく。標準語だけだと、どうしても土地を描くにはシンプルになりすぎてしまう。なので、実をいうと、苦しいときに方言のパワーを借りようとするところがあります。『月ぬ走いや』はすべて一人称の十四篇で構成したんですが、『はくしむるち』の場合はいろんな人称や視点を交えているので、なかなか全体の見通しがつきにくかった。そこで「むるち」をはじめ沖縄語のパワーを取り込んでいくうちに、少しずつ小説の推進力が増していった気がします。
 豊永浩平さん(撮影 森清)
豊永浩平さん(撮影 森清)
池澤 でも、それが力になっているし、ルビの使い方もうまいですね。日本語には漢字で意味を伝えた上で、響きをルビで伝えるというやり方がある。それをこの小説の場合では沖縄語(うちなーぐち)に応用して、とても成功していると思う。
豊永 沖縄の作家でいえば、大城立裕さんもすごく言語に関心のある方でしたよね。芥川賞を受賞した「カクテル・パーティー」では、いろんな言語がざわめく中で小説の場が形成されていく。言語同士の引っ張り合いみたいに、沖縄語(うちなーぐち)があって大和口(やまとぐち)があり、昔の琉球王国時代には漢文を基礎とした中国語があって、戦後はアメリカの英語がある。その言語同士の引っ張り合いを、僕は国家間の力関係みたいな感じで捉えていて、自分の小説でも、土地の境目であると同時に、言語の境目でどう考えていくかということを、かなり意識して書くようにしています。
池澤 そういう言語の問題意識は、日本の他のどの土地でもあり得ないわけですよ。
たしかに沖縄という土地の運命を書くという点で、この小説に一番近いのは大城さんですね。彼がやろうとしたことを、さらに先のほうへ進めて、ここまで伸び伸びと大きな作品にしたのは、豊永さんの力だと思います。