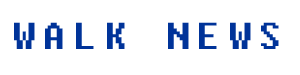四半世紀にわたり実質的な独裁者として君臨してきたロシアのプーチン大統領。東京大学の池田嘉郎教授は、新刊『悪党たちのソ連帝国』(新潮選書)において、ソ連時代の6人の指導者を振り返ることによって、その「鉄拳独裁」の秘訣に迫っています。同書の「プロローグ」の一部を抜粋・編集し、試し読みとして公開します。
大家族ソ連
本書では、強力な意志によって国家を統治した6名の人物を通して、ソ連史におけるジグザグについて、そしてまたソ連史を貫く連続性について語りたい。現代ロシアについても論ずべきことは多いが、本書ではソ連史に力を注ごう。1917年の革命から1991年のソ連崩壊まで、その74年の歴史は本当に多くの出来事に満ちているのであるから。
ソ連史のジグザグはそれぞれの章を追っていけば見えてくるであろうが、そこを貫く連続性についてはここで一言述べておきたい。歴代の指導者の個性は様々であったが、彼らがみな念頭においていたことがあった。それは、ソ連という一つの共同体を守り、発展させねばならないということである。ソ連とは国家であるのだが、単にそれだけではなかった。なぜならば、その国家を機能させるための重要な要素として、共産党という団体があったからである。レーニンにとって共産党とは、成員ひとりひとりがエゴイズムを捨てて全体のために活動する、大きな家族のようなものであった。共産党におけるこの家族的イメージは、スターリンのもとでソ連市民全体に広げられた。以後の指導者は、家族共同体としてのソ連を受け継ぎ、発展させようと努めた。
家族的な共同体という像は、正教会やロシア思想において好んで使われるサボールノスチという語とも重なる。はじめに個があるのではなく、まずは全体があって、そうした全体と不可分のものとして個がある。大まかにいえばこれがサボールノスチである。共同性と訳してもよいであろう。
ソ連とは、強力な指導者のもとに統合された巨大な共同体であった。その個々の成員は、近代ヨーロッパの用語を借りて、ソ連「市民」と呼ばれた。だが、近代ヨーロッパ、とりわけフランス革命によって打ち出された、個人としての権利をもつ「市民」の姿と、ソ連市民の像は必ずしも同一ではなかった。近代ヨーロッパにおいて、個としての市民を支えた重要な制度は私的所有権であるが、ソ連の法文化では私的所有権は冷遇された。国家こそが第一の、いたるところで現れる、所有者であったからである。個人としての市民が主人公となる近代ヨーロッパ社会とは、ソ連は異なる原理に基づいていた。
私的所有権をよりどころとする市民が、法の力で権力者を抑制するところに、近代ヨーロッパ諸国の特徴があった。これに対してソ連では、法は権力者が市民を規制するための手段であった。この点でソ連はむしろ、皇帝が君臨した革命前のロシアに似ていた。統治者が法の上に立っている点、それにくわえて、広大な領域と多様な住民集団をもつ点をもって、本書では「帝国」という言葉を使いたい。ソ連は20世紀の帝国であった。
この「帝国」=家族共同体の長をつとめた、ウラジーミル・レーニン、ヨシフ・スターリン、ニキータ・フルシチョフ、レオニード・ブレジネフ、ユーリー・アンドロポフ、ミハイル・ゴルバチョフという6人の最高指導者のことを、1章ずつを割いて論じたい。彼らは大国の指導者として権力を振るい、多くの人間の生き死にを左右した。そうした権力の巨大さを表現するために、本書では「悪党」という言葉でソ連の歴代指導者を呼んでみたい。これは必ずしも道徳的な善悪を含意していない。ソ連指導者が行使した権力と、それによって起こった変革、および彼らがもたらした犠牲は、あまりにも大きく、道徳的な尺度で計るのには適していないからである。そもそも歴史学は、よいことや悪いことを語る学問ではない。
それにしても、もし指導者の視点だけに即して語るのであれば、彼らの行ないを無批判的に受け入れることにつながりかねない。誰か、リーダーたちの振舞いを、脇のほうから見てきた人物はいないであろうか。そうした人物の助けを借りれば、強力な「悪党」たちの振舞いを相対化できるのではないだろうか。
できればソ連の74年間を、最初から最後まで歩んだ人物を見つけるのがいい。先ほど見た国歌作詞者セルゲイ・ミハルコフ(1913—2009年)も候補となろう。だが、彼は国歌を1度ならず書いただけに、やや指導者たちに近すぎるように思われる。ちなみにその息子の1人が、映画監督としてソ連後期から現在にかけて活躍し、近年では愛国主義的な発言が目立つニキータ・ミハルコフである。共産党中央委員会ビルのあるスターラヤ広場から、もう少し距離をおいて仕事をしてきた人を見つけたい。
ここで私が思い出すのは、2001年の新国歌制定にさきだって、その是非をめぐって行なわれたあるテレビ討論である。賛成論者のなかには、オリンピックに出るような優れたスポーツ選手がいた。彼によれば、自分たちはソ連国歌の旋律のもとで表彰を受けてきた、いまのグリンカの国歌ではなかなか頑張ろうという気が起きない、というのである。これに対する反対論者の一人が、モスクワ・タガンカ劇場の総監督ユーリー・リュビーモフ(1917—2014年)であった。世界的に知られるこの演出家は、あの旋律のもとでわれらの祖父母や父母の世代の人々が銃殺されてきたのではないかと述べたのである。十月革命の直前に生まれ、ソ連後半に政権の文化統制にさんざん苦労してきたリュビーモフの目を通せば、帝国のありようを指導者とは別の視点から照射することができるのではないだろうか。
とはいえリュビーモフのことを、共産党政権の抑圧に抵抗してきた闘士だなどと大げさに持ち上げる必要はない。彼もまた、ソ連という大家族のなかで育ってきた人なのだ。総じて抑圧と抵抗のような単純な図式は、ソ連帝国という複雑な有機体を解剖するのには適さない。大事なことは、強力な共産党書記長であれ、優れた舞台監督であれ、その他大勢のソ連市民であれ、どのようなことを語り、どのようなことをしてきたのかを、その時代の文脈のなかで見てみることだ。それを確認したうえで、悪党たちのソ連帝国の物語を始めよう。
(以上は本編の一部です。詳細・続きは書籍にて)