 (c)堀田力丸 2021年からロイヤル・リヴァプール・フィルの首席指揮者を務める、ベネズエラ出身のドミンゴ・インドヤン。細身の長身、いかにも今ふうのカッコイイ若者だが、音のつくりはとても生真面目。そのギャップが面白い。
(c)堀田力丸 2021年からロイヤル・リヴァプール・フィルの首席指揮者を務める、ベネズエラ出身のドミンゴ・インドヤン。細身の長身、いかにも今ふうのカッコイイ若者だが、音のつくりはとても生真面目。そのギャップが面白い。
柴田俊幸&アンソニー・ロマニウクのデュオ・リサイタル…古今の楽器で混交の調べ
もっとも、最初のルーセル「バッカスとアリアーヌ」第2組曲では、そうした個性に気づかなかった。オーケストラの奇妙な味わいに気をとられてしまったためだろう。弦楽器群はやや非力ながらも、木管と金管の音色に不思議なムラがあり、それがなんともチャーミングなのだ。次はどんな音がするのかと、思わず待ちかまえてしまう。
「生真面目さ」をはっきりと意識したのは、ショスタコーヴィチの交響曲第5番の第1楽章コーダ。
常套(じょうとう)
的なテンポのゆるみがなく、きっちりと句読点を打つようにしてピアニシモが行進してゆく。弱音のなかにみっしりとエネルギーが充満しているから、ごく
些細(ささい)
な和声の変化がはっきりと感じとれる。
いったん意識してみれば、硬く凝縮された響きが続いた第2楽章も、途中でフォルテシモが風船のようにいきなり膨らんだ第3楽章も、さらには階段を降りるようにしてカクカクと減速していった終楽章も、きちんと楽譜の指示を守っており、奇抜な仕掛けなど何もないことがよく分かる。それでも新鮮に響くのは、これまでの演奏慣習から身を引き剥がして楽譜を読むことができるからだろう。これは簡単なようでひどく難しいことだ。 あいだに挟まれていたのが、辻井伸行の独奏によるラフマニノフのピアノ協奏曲第2番。このひとのピアノには、その場で即興しているかのような独特のライヴ感がある。会場が熱狂するのも当然だと得心した。(音楽評論家・沼野雄司) 14日、赤坂・サントリーホール。
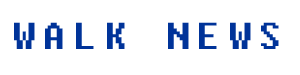
![[音楽] ドミンゴ・インドヤン指揮のロイヤル・リヴァプール・フィル…生真面目な音、新鮮な響き [音楽] ドミンゴ・インドヤン指揮のロイヤル・リヴァプール・フィル…生真面目な音、新鮮な響き](https://www.walknews.com/wp-content/uploads/2024/06/1717236320_20240528-OYT8I50068-1-1024x576.jpg)