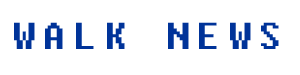こんにちは。メディカム編集部 経営企画チームです。
メディアドゥは、電子書籍取次事業者として2,200社以上の出版社、150店以上の電子書店の間に立ち、出版業界全体の発展に貢献することを目指してきました。将来にわたって必要とされる企業であり続けるためには、出版業界の成り立ちや特性を深く理解しながら、この先訪れる未来を様々な視点から想像し、出版業界の方々と共に新しい時代をつくるイノベーションを模索していくことが求められます。
そこでメディカムでは、文芸編集者を振り出しに40年以上もの間出版業界で活躍し、メディアドゥ副社長 COOを経て現在は上級顧問を務める新名新氏による連載を2024年11月より開始しました。新名氏が見る業界の成り立ちや社会の動向を踏まえた、「出版の未来」を4回にわたって掲載しており、今回が最終回となります。
メディアドゥ 上級顧問 新名 新(にいな・しん)
1954年生まれ。1980年(株)中央公論社入社。吉行淳之介、司馬遼太郎、筒井康隆、村上春樹、内田康夫などの編集者を担当。1996年(株)角川書店(現・KADOKAWA)入社。2007年同社常務取締役就任。電子を含む出版部門、海外版権部門を統括し、モバイルブック・ジェーピー、リブリカ、ブック・ウォーカーなど電子出版関連企業の社外取締役を務める。2014年(株)出版デジタル機構代表取締役社長就任。2018年(株)メディアドゥホールディングス(現・メディアドゥ)副社長就任。2024年より上級顧問。

<バックナンバー>
第一回 https://mediado.jp/medicome/industry/7738/
第二回 https://mediado.jp/medicome/industry/8134/
第三回 https://mediado.jp/medicome/industry/8384/
出版における著作物というものは、出版産業をめぐる環境とテクノロジーの変化によって、15年後にはどのようになっているのだろうか。最終回となる今回は、その予測をしてみたい。ただ、現在の著作物の形態や在り方が、2040年にすっかり消滅している可能性はないだろう。人類の歴史の中でしぶとく生き残ってきた紙と印刷による書物はそう簡単に滅びないし、その形式を前提とした著作物も15年後にはかなりの割合で生き残っているに違いない。
新しい著作物はどこから生まれてくるのか
すでに現在、新しい作品は出版社を窓口として誕生するだけでなく、Webを舞台としたプラットフォームからも生まれている。著者自らが著作物をWebのプラットフォームで直接発表するという傾向は、今後ますます強くなるだろう。文芸系、学術系、実用書系といったジャンルを問わず、Webを通して著者が直接読者と繋がる形の出版は当たり前となる。
そこでは、現在主流の投稿サイトだけでなく、ジャンルに応じた様々な形式のプラットフォームが生まれるだろう。文芸系では、作家と読者を結ぶプラットフォーム構築を支援するサービスが多く生まれる。学術系では、世界的規模の学術出版企業に寡占されている学会雑誌を中心とした論文発表の仕組みが、時間を要する査読の煩わしさや、寡占そのものを嫌う研究者の意向によって、次第に変化する。実用書系では、その目的に必要な教育や物販のサイトと融合した著作物の配信が主流となりそうだ。
このような未来に生じる問題点は二つある。一つはコンテンツの質的担保、もう一つはマネタイズの方法である。誰もが自由に著作物を発表する世界で、読者はどのように作品を発見し、その対価を支払うことになるのか。
前者については、ブランディングが重要となる。プラットフォームなのか、著者名なのか、はたまた「いいね」の数なのか、いずれにせよ読者の信頼を得たブランドにアクセスが集中するのは現在と同様である。そこには、ブランド力を持つ既存出版社の出番もあるだろう。
後者のマネタイズは難しい課題である。これまでは出版社が、売れる出版物の収益を一部留保して、新人の作品などマネタイズの難しい出版物の刊行に投資してきた。このサイクルによって、次のマネタイズができる出版物も生み出されてきたのである。しかし出版社という緩衝役のいない場では、アクセスの集中する著作物に収益も集中し、それ以外はマネタイズできないという傾向が現在よりも強く表れる。著者自らが投資を行うか、マネタイズに重きを置かない副業としての著作者が増加することになるだろう。よい作品を発見するための負荷もどんどん増えてしまう。
実は質的担保とマネタイズは密接に関係している。hon.jpの主宰者、鷹野凌氏はこれを「価値ある情報の多くがペイウォールの向こう側にある状態になる」と表現している。Web世界には玉石混淆のコンテンツが百花繚乱のごとく存在するが、良質なコンテンツは、しかるべき対価と引き換えでなければ入手できないのだ。
文芸作品はどこへ行く?
文芸作品の大きな変化は、パッケージ型書籍の枠を超えるところから始まる。現在の長編小説は、1冊の書籍というパッケージのせいで長さに制約がある。映画が映画館の上映回数の制約から2時間程度の長さになっているのと同様、分厚かったり、上下巻になったりすると本が売りにくいという出版社の意向で、長編小説の長さは一定の範囲に収まっている。短編集も1冊の本に入る分量をもとに収録作品数が決められてきた。もちろん例外はあるが、多くはこの制約を受け入れてきた。しかしこれも、動画の世界同様、配信に主力が移っていくと長さの制約はかなり緩和され、創作の自由度があがる。
さらにパッケージの縛りがほどけていくと、先に述べた配信プラットフォームの多様化とも相まって、まったく新しい小説形式が誕生するかもしれない。たとえば結末のない小説、一つの世界観の中で延々と異なるエピソードが紡がれ、しかも複数の作家がそれに参加するような、そうした小説の表現形式である。これは私の予測ではなく、SF作家藤井大洋氏から聞いた話であるが、これも文芸のデジタル化によって可能になる未来の一つだ。
いずれにせよ、紙の書籍が課していた文芸創作への制約は、電子化によって大きく緩和されることになるだろう。小説とAIの関係については後に述べたい。
マンガはどこへ行く?
マンガ作品について確実に言えるのは、日本マンガの国際的な浸透と拡散である。ここで言う日本マンガとは、作者の国籍や民族性とは関係なく、コマ割があり、ページを単位とし、吹き出しの中に台詞が記述されるという、現在我々が親しんでいる日本的マンガのことである。
日本国内のマンガが既に持つ特筆すべき特徴として、内容の豊富さがあげられる。歴史、哲学、科学、職業生活、学園生活、ロマンス、ミステリー、SF、そしてシリアスからギャグに至るまでかなり広汎にわたっており、海外のグラフィック・ノベルと比較すると、はるかに広い内容を扱っている。このような表現形式は今後もありとあらゆる民族、文化の国々に受容されていくだろう。一方、日本から輸出された作品に影響を受けたそれぞれの文化圏では、独自の作家たちが誕生し、日本マンガの形式で自らの作品を生み出し始めることは必然である。
柔道や寿司といった日本独自の文化が国際化によって変容してきたように、マンガも新しい表現を獲得し、それが日本に逆輸入されることも当たり前になるだろう。既に日本人は、『マトリックス』のウォシャウスキー姉妹や『グランド・ブダペスト・ホテル』のウェス・アンダーソンのように、日本のマンガやアニメに強く影響されたハリウッドの映画監督たちの作品を広く受け入れている。
マンガはモノクロのスクリーントーンで表現されるべきか、カラーであるべきかという議論もある。これはあまり大きな問題ではなく、これまでは印刷コスト、制作コストの面でカラーが難しかったが、電子コミックやAI制作の進展により問題は解決されていく。作者は表現形式を自由に選択すればよいのである。
マンガの範疇に入れるべきかどうかはさておき、縦スクロールのような電子独自の新しい表現形式も次々と開発されるだろう。現在はスタジオ形式で多数の人間がかかわっているためコストのかかる縦スクロールも、AIの支援によってごく少数の作家とアシスタントだけで制作が可能になりそうだ。韓国のスタジオ形式でなく、従来の日本マンガと同様の制作手法でも、縦スクロールをはじめとするグローバルマーケットを狙った新しい表現形式の作品を描くことが可能になる。
AIは作品の創造にどう関与するのか
AIは2040年の出版に様々なところで関わってくるだろうが、ここでは創作への関与に絞って語りたい。もともと生成AIは普通のコンピュータのように正確で論理的な出力は苦手だ。同一のプロンプトであっても、都度ごとに異なる出力が生成されてしまう。しかし、新たに何かを生み出すことは得意であり、作品創造との親和性は高い。
生成AIに創作は可能か、という議論がよくある。人間が鑑賞して創作物だと認識できるコンテンツを生み出すことが「創作」だとすれば、既に生成AIは創作が「可能」である。15年後には生成AI技術の進化および学習の深化によって、現在よりさらに多くの、かつ人間が高評価を与える作品が生み出されることになるだろう。
ただ、優れた作品のみをAIが創作してくれれば話は簡単なのだが、15年後であっても、少数の秀作と同時に大量の凡作が生成されるに違いない。結局、人間によるものであれAIによるものであれ、生み出された著作物の価値を判断するのは目利きの人間ということになる。となれば、少なくとも編集者の将来には少し希望が持てそうだ。
現在の投稿サイトのように、Webに集う多くのユーザが目利き役を務めるという方法もある。だが今でも、この多数ユーザと少数編集者の評価は往々にして一致しない。投稿サイトのランキングでさほど上位にない作品に編集者が目をとめ、実際に刊行してみたらベストセラーになった、という例は枚挙にいとまがない。多くの人々が高く評価した作品をAIに学習させ、人間の代わりに評価をさせようとしても、結局こうした事例と同じになるだろう。多数の評価というのは「過去」の評価の集大成であり、ごく少数のこれから評価されるものを発見するには不向きである。
文章を生成するAIの仕組みをむちゃくちゃ簡単に言ってしまうと、過去の学習結果をもとに、次に来る言葉を確率の高い順に選択して並べて行くというのが基本原理である。しかしそのAIでさえ、最も高い確率の単語100%を並べて生成された文章より、20%はより低い確率の単語を交えて生成した文章のほうが、人間からは高い評価が得られるのだそうだ。なぜ20%なのか、現時点でその理由は解明できておらず、経験値によるという。
大量の学習によって得られた最高確率100%が多数決によるユーザ評価に当たり、20%が個人の目利きによる評価に類するものなのかもしれない。
さて、AIが文芸系の創作に与える影響は大きく二つあると考える。
一つは、大量に創作物を生み出すことで、その取捨選択という問題は残るにせよ、作品の供給量が飛躍的に増えるということだ。作品を受容する側はそれほど増えないので、人間の著者は限られた市場でAI著者と競合することになる。取捨選択がうまく機能しないと、世の中は凡作であふれかえり、出版に限らずコンテンツ・ビジネスが成立しなくなる可能性すらある。そうなると、人間が創作したという保証付きの作品に注目が集まることも考えられる。
もう一つは、人間の創作者がAIの創作を利用することで、作品の質を上げ量を増やす可能性である。生成AIの利用に長けた著者は、その支援によって自らの著作物の幅を拡げることができるだろう。特殊な実験的文学のジャンルでさえ、生成AIの利用によって、これまでにない画期的作品が生まれるかもしれない。
過去の出版界には、年間10冊もの作品を刊行しながら、それぞれがベストセラーになるという多作の人気作家が存在した。漫画家でいえば手塚治虫の超人的仕事ぶりが有名である。生成AIの創作支援は、一定の質を維持したまま、再びこのような多作作家を登場させる可能性がある。
また韓国では、既存の画像生成AIに作風を学習させるというファインチューニングを施し、これを利用して作品を描き続けている縦スクロールコミックの作家も現れた。この作家の願いは、自らが生み出したキャラクターが作者の死後も物語を紡ぎ続けることだというが、生成AIはそうしたことも可能にする。しかし同時に、第三者がある著者の作品を学習させてしまえば、その著者の作品に見えるフェイクを生成することも容易である。しかも、このフェイク作品がオリジナルの文章やキャラクターなどを含まず、オリジナルの作家名で発表されなければ、法的にも問題にならない可能性が高い。
学術系ジャンルでも、生成AIの影響は大きい。質のみならず、量と速度も重要である学術論文などでは、生成AIの利用が研究者にとって必須となる。学術論文ならではのフォーマットに合わせた整形、図版や表の作成、他の著作物の要約、論文内容の査読評価などはAIが代替しているだろう。
実用書でも同様に、生成AIの執筆支援が当たり前となる。特定の読者層を想定した文章の書き換え、内容の理解を助けるイラストの制作など、様々な支援が考えられる。著者の過去の著作物を学習させておけば、箇条書きのプロンプトを与えるだけで、その著者の語り口に即した文章を生成してくれる。
またすべてのジャンルに当てはまることだが、出版社の編集者が果たしている役割のひとつ、文章や内容に関する著者へのアドバイスはある程度AIで代行できるだろう。現在の生成AIでも、文章に対する評価、代替案とその提案理由など、メンター機能はかなり充実している。この能力も2040年には飛躍的に強化されていると考える。現在の生成AIで問題となっているハルシネーション(事実と異なったり存在しない情報を出力してしまうこと)も急速に改善しつつあり、完全に人間を代替することは難しいだろうが、執筆のための調べもの、校閲などに利用することも現実的になる。
こうして著作物の創造に広くAIが利用される時代に生じるのが、「著者」の概念に関する問題である。次の項では、著作権が15年後にはどうなっているのかを論じてみよう。
著作権はどう変化するのか
法律というものの性質上、社会の技術的革新に即応できないのは致し方ないところである。よって、2040年に著作権がどう変化しているかという問いに対する答えは、これから10年後くらいまでに進展する技術を、その5年後に法律がどのくらい呑み込んでいるかという予測になる。とは言っても、AI技術の発達はこれからの10年間だけでも相当なものになると予測され、著作権の変化も推測が難しい。
最初に、AIの学習に著作物を利用する場合を考えてみよう。
人類に役立つAIを育てるためには、人間と同じで良質の学習が必要である。AIは学習によって、非道徳的になったり偏見を持ったりしてしまう。こうした事態を避けるためには、良質の著作物で学習させるのが一番である。この場合、著作権の利用をどう考えるのかが当面の課題となる。
この5月に営利企業化を断念したOpenAIなど一部を除けば、多くはGoogle、Microsoft、METAなど大企業の提供する営利を目的としたサービスであり、高度なバージョンについては対価を必要とする場合がほとんどである。当然、営利目的AIの学習に使用するのであれば、著作権者は権利を主張するであろう。一方で、著作物を利用される著者の側も、良質のAIを利用することで得られる利益がある。いつの時代であっても、著作者は過去の著作物の恩恵のもとに自らの著作物を創造してきた。今後は、この恩恵の中にAIが加えられることになるからだ。
このような観点から、現行著作権とAI学習への利用との間でバランスを取ることが、これから数年間に必要となる。学習の結果、AIがもとの著作物と同じものを一定量以上出力できるとなると、これは現行著作権法でも違法である。しかし、この問題は現在の技術でも制限できる。となると、著作権利用の対価をどう考えるかが一番の焦点になりそうだ。いずれにせよ、あと5年ほどで法整備が行われ、この問題は解決するであろう。1点1点の作品を管理することは非現実的なので、教育におけるデジタル著作権利用を目的に設立されたSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)のような仕組みが導入されることも考えられる。
先の事例で述べた、著作者自らが望んで死後に生成された作品と、第三者によって作成されたフェイク作品の著作権的問題なども含め、2040年には、AIを利用した著作物の著作権について、法的整理が終わっていると期待したい。しかしそこまでの道のりは簡単ではないだろう。
現状では海外も含めて、AIによる生成物の著作権が誰に帰属するかは、状況によって異なるという解釈が主流である。日本では、コンテンツ制作のツールとしてAIを用い、「思想や感情を表現する作品」を創作しようとしてプロンプトを入力した場合、その入力者である人間が著作者として認められる可能性はあるとの文化庁見解が示されている。
最近、スタジオジブリ風の画像がAIで作成されて話題になったが、こちらは現行著作権法でも違法とはならない。アイディアや作風は著作権保護の対象にならないからである。しかし、このようにして生成した○○風の画像に対して、これを生成した人間が著作権を主張するとなると、多くの人々は納得できないだろう。だが、前述の文化庁見解の延長では、これが認められてしまう可能性がある。AIを利用せず、人間がジブリの作風でオリジナルのキャラクターを描けば、現在の法律ではその作品に著作権が発生するのと同じである。文章でも、ある著者の作風で執筆された作品というだけでは違法とならない。
また、AIの生成物に人間が手を加えて作品を制作した場合、その程度に応じて著作権が発生するのは当然であろう。こうした状況下では、プロンプトを入力した人間と、その出力結果に手を加えた人間の双方が著作権者になるという可能性も考えられる。
ただし、先に述べたように、AIの生成物なのか人間の著作物なのか区別が付かなくなる将来、著作物が人間の創作なのか、AIの生成物なのか、人間とAIの合作なのかを第三者が客観的に判断することは相当困難である。また、大量に生成した作品の中から「これは」と思う作品を選び出す行為そのものが、現行法で言うところの編集著作権として認められるかもしれない。こうした状況を整理した結果、15年後の著作権法は大きく変化している可能性が高いが、それを予測するのは正直難しい。案外、AIによる自動運転車の事故責任の所在などと法的整合性が図られるかもしれない。
いずれにせよ、これまで拡大が続いた人間の著作権には、何らかの制約が課せられる方向に進むのではないかと考えている。
【連載を終えるに当たって】
今から15年後の2040年を予想するという口実でいろいろと言いたいことを書いてきましたが、こと出版に関する限り、紙と印刷による冊子形式というメディアは2040年もしっかり残っていると思います。また、そうしたメディアに関わる人々、企業も、規模は小さくなるかもしれませんが、かなりの割合で生き延びると考えています。
一方で「出版」という概念は拡大し、出版物の制作や物流をめぐる環境の変化、AIを筆頭とする新しいテクノロジーの進展などを呑み込んで次のステージに進化しそうな気配を感じます。
角川アスキー総合研究所主席研究員の遠藤諭氏に教えてもらったダグラス・アダムスの法則というものがあります。この人物は『銀河ヒッチハイク・ガイド』というシリーズで知られる英国のSF作家なのですが、下記のような法則を提唱しました。
生まれたときに世の中にあったものは、普通で当たり前で、世界を動かす自然の一部である
15歳から35歳の間に発明されたものは、刺激的で革命的と感じ、その分野でキャリアを積むこともできる
35歳を過ぎてから登場してきたものは、自然の秩序に反するものである
現在71歳の私にとって、2はPC(パーソナルコンピュータ)とインターネットの出現でした。そして、出版界という限定付きですが、こうした分野でキャリアを積んで来ました。しかし、AIは私にとって3に当たります。最終回のためにAIに関する書物を読み漁りましたが、それでもこのような感覚は払拭できませんでした。これからの出版界でも、AIの出現を15歳から35歳で経験した世代が新しい時代を作っていってくれるのでしょう。
受動的に楽しめる音楽や動画と異なり、能動的に関わらないと鑑賞できない出版物には、社会や文化の中で果たすべき独自の役割があると思っています。それは技術や経済の環境が変わっても不変のものです。変わらぬ価値を大事にしつつ、変わるものを積極的に取り込んで、2040年の出版をより良きものにしていただきたいと願いつつ、この辺で筆を擱くことにします。長期にわたる連載企画に最後までお付き合いいただいた読者のみなさんに感謝いたします。
読了後アンケートご回答のお願い(1分程度)
本連載やMedicome!について、下記URLよりご感想・ご意見をお寄せください。
https://forms.gle/WB8DoHF8ZKcM2b1L9