人の痛み ピント合わせ 安川純撮影 先日、スマートフォンに収められている写真を何げなく眺めていると、実に数万枚もの写真が保存されていたことに驚いた。レストランで出された料理、仲間らとの集合写真――。同じような構図のものが何枚もある。ほかにも、切り抜き代わりに撮った新聞紙面や、居場所を知らせる目的で撮った街角など、いわばメモのように、1日に何枚もの写真を、ちゅうちょなく撮っている。スマートフォンのカメラ機能も、目を見張るものがある。画面をタッチすれば、明るさの補正やピント合わせも自動で、“いい具合”に行ってくれる。
安川純撮影 先日、スマートフォンに収められている写真を何げなく眺めていると、実に数万枚もの写真が保存されていたことに驚いた。レストランで出された料理、仲間らとの集合写真――。同じような構図のものが何枚もある。ほかにも、切り抜き代わりに撮った新聞紙面や、居場所を知らせる目的で撮った街角など、いわばメモのように、1日に何枚もの写真を、ちゅうちょなく撮っている。スマートフォンのカメラ機能も、目を見張るものがある。画面をタッチすれば、明るさの補正やピント合わせも自動で、“いい具合”に行ってくれる。
[深層NEWS]政治資金問題…下村博文氏「岸田首相はもう一度、森喜朗・元首相に関与の有無聞いて」
大学時代、私は写真部に所属していた。学校帰りに、一眼レフのフィルムカメラをぶらさげ、あてなく街を歩きながら、思いのままシャッターを切るのが好きだった。新緑の木々から差し込む木漏れ日、スクランブル交差点を行き交う人々――。ふと立ち止まって、四角形のファインダーをのぞくと、見慣れた街の景色に特別な意味づけをするような感覚がわいた。「ガシャ」という低いシャッター音の響きは、その瞬間の心のありようを切り取る合図にも感じた。 5月中旬、久々に母校の大学を訪れる機会があった。いまは、高層ビルを中心とした先進的なキャンパスだが、私が通っていた頃は、背の低いどっしりとした、たたずまいの校舎だった。薄暗い階段の踊り場に、学生闘争時代の名残を感じさせる黄ばんだビラが貼ってあったり、廊下の隅にいつからそこにあるかわからない文庫本が落ちていたりしていた。時が止まったような古い校舎の一角や、屋上から見える建設途中の六本木ヒルズに、よくカメラを向けていた。 写真部の部室の奥には、小さな暗室があった。現像用の溶液の酸っぱいにおいが漂い、感光しないためのぼんやりとした赤い明かりのもと、試行錯誤しながら何時間もかけて1枚のモノクロ写真を現像した。レンズから入る光量を調節する絞りや、ピントが合っていないことも多く、何度も悔しい思いをした。部室では、思い思いに撮影した写真を部員らと品評しあった。次第に熱を帯び、1枚の写真を巡って延々と写真談議を交わした頃が懐かしい。
フィルムカメラは、いま、私の自室の棚に静かに置かれている。ひんやりとした手触りと、ずしりとした重みを感じながら、かつて36枚撮りのモノクロフィルムを
装填(そうてん)
し、どう撮るかを考えながらシャッターを切った日々を思い出した。
いま、スマートフォンを開けば、大量の写真と同様に、大量のニュースも並んでいる。その見出しは刻々と変わり、すくい上げるまもなく過ぎ去っていく。しかし、そのニュース一つ一つには、穏やかな日常が、突然奪われた怒りや悲しみ、月日がたっても決して癒えることのない痛みがあることを、忘れずにいたい。ニュースに携わる一人として、かつてフィルムカメラを手にした頃のように、社会の光量を見極め、ピントを大事に合わせたい。そして、切り取った現実に対して、スタジオで熱を帯びた議論を交わしたい。(BS日テレ「深層NEWS」キャスター)
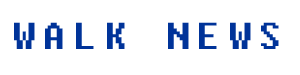
![[テレビ] [深層一直線]スマホ時代の写真談議とは…右松健太 [テレビ] [深層一直線]スマホ時代の写真談議とは…右松健太](https://www.walknews.com/wp-content/uploads/2024/06/1717403423_20240603-OYT1I50082-1-1024x576.jpg)