フィクションで子供を描く時、
無垢(むく)
で汚れのない存在として描かれがちだ。そうあってほしいという大人側の願いもあるだろうが、実際はもっと複雑で、油断ならない側面もあるはず。幻想に満ちた子供像を覆し、教育や児童福祉のあり方を問う映画の公開が相次ぐ。教員のオーバーワーク、画一的な学びの弊害が指摘される日本とも共通する問題を扱っている。
 「ありふれた教室」 きょう公開の「ありふれた教室」(イルケル・チャタク監督)=写真=は、金品の盗難事件が相次ぐ中学校が舞台。犯人捜しを巡って、激しい論争が巻き起こり、学校崩壊に陥るスリラーだ。
「ありふれた教室」 きょう公開の「ありふれた教室」(イルケル・チャタク監督)=写真=は、金品の盗難事件が相次ぐ中学校が舞台。犯人捜しを巡って、激しい論争が巻き起こり、学校崩壊に陥るスリラーだ。
学園ものは教員と児童生徒の心温まる交流や絆を描くのがお決まりだった。本作では子供たちは公然と大人に反旗を翻す。 先に公開された欧米での反響を受け、米アカデミー賞の国際長編映画賞部門にノミネートされた。熱意や善意が空回りする教員カーラ役のレオニー・ベネシュは「学校は、社会に出るまでに最初に放り込まれる場所。世界中のほとんどの人が関わる普遍的な場所だからこそ物語も伝わった」と話す。 子供を、未熟で従順な存在だと侮っていないか。見る人もそうした甘い考えに気づかされる。「(生徒役の)子供たちは非常に多様だけれど、現実を反映しているだけ」とベネシュ。「人間は集団になれば、いさかいが起こるもの。ささいなことが誤解されることもある。良い人に見られたいという願望、注目を集めようとケンカ腰になることも現実社会によくある。見るたびに新たな発見がある美しい映画です」と語る。 「システム・クラッシャー」 公開中の「システム・クラッシャー」(ノラ・フィングシャイト監督)=写真=は既存の社会システムを揺るがす“超問題児”を描く。感情のコントロールができない9歳の少女ベニーは教室どころか、家庭にも居場所がない。特別な支援を受けられるグループホームを転々とするが、各方面の専門家による試みも失敗に終わる。 取り巻く大人たちは、いつか思いが通じ、苦労は報われるという希望を打ち砕かれ、心身を消耗させていく。問題行為の背景には、幼少期のトラウマがある。親にも学校にも福祉にも見放された場合、誰がその子に寄り添うのか。ピンク色が大好きで、一見、西洋画の天使のように愛くるしいベニーが突きつける課題は深刻だ。
「システム・クラッシャー」 公開中の「システム・クラッシャー」(ノラ・フィングシャイト監督)=写真=は既存の社会システムを揺るがす“超問題児”を描く。感情のコントロールができない9歳の少女ベニーは教室どころか、家庭にも居場所がない。特別な支援を受けられるグループホームを転々とするが、各方面の専門家による試みも失敗に終わる。 取り巻く大人たちは、いつか思いが通じ、苦労は報われるという希望を打ち砕かれ、心身を消耗させていく。問題行為の背景には、幼少期のトラウマがある。親にも学校にも福祉にも見放された場合、誰がその子に寄り添うのか。ピンク色が大好きで、一見、西洋画の天使のように愛くるしいベニーが突きつける課題は深刻だ。
奇(く)
しくも両作とも移民国家で、多様性を掲げるドイツで制作された。異なる個性や価値観を認め合うということは、時に衝突や痛みも伴う。子供のまなざしから、現代社会の普遍的な課題を指摘している。(木村直子)
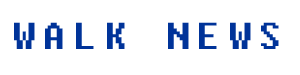
![[映画] [週刊エンタメ]<トレンド>「無垢ではない」子供の目から 教育や福祉 あり方問う 独映画2作公開 [映画] [週刊エンタメ]<トレンド>「無垢ではない」子供の目から 教育や福祉 あり方問う 独映画2作公開](https://www.walknews.com/wp-content/uploads/2024/05/1715894661_20240516-OYT8I50105-1-1024x576.jpg)