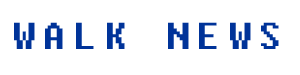vandervelden/iStock
「太ったのは本人の自己責任か?」
この問いに対し、イギリスは近年、はっきりと「NO」と答え始めている。
肥満は意志の弱さの結果ではなく、産業と制度が作り出した環境の帰結であり、その責任は個人だけに帰せない。
これが現在のイギリスの公式な問題認識である。
イギリスの成人肥満率(BMI30以上)は約29%に達している。過体重(BMI25以上)まで含めれば、成人の約65%が該当する。これは高所得国の中でも最悪水準だ。対照的に、BMI30以上の日本の成人は男性で約4%、女性で約3%にとどまる。いかにイギリスで肥満が蔓延し、深刻な社会問題となっているかが分かるだろう。
イギリスでは、肥満はすでに「個人の生活習慣の問題」ではない。政府、議会、医療当局は一貫して、肥満を「長期にわたる公衆衛生上の危機」と位置づけている。その最大の理由の一つが、国民保健サービス(NHS)への深刻な負荷である。NHSは税財源で運営される国営医療サービスであり、肥満の増加は医療費の膨張として直撃する。
肥満および関連疾患による医療費は、年間約110億ポンドに上るとされる。日本円に換算すれば約2.1兆円だ(1ポンド=約190円換算)。さらに、生産性低下や社会保障費を含めた社会的損失は、GDPの1〜2%、年間300〜600億ポンド(約5.7〜11.4兆円)に達する。肥満は、健康問題であると同時に財政問題でもある。
NHSの待機リストが長期化し、医療従事者の負担が限界に近づくなか、肥満対策は「望ましい健康づくり」ではなく、「医療制度を守るための国家戦略」として扱われている。ここに、日本との決定的な違いがある。日本では医療費増大が問題視されつつも、肥満は依然として個人の自己管理の問題として語られがちだ。
こうした危機認識のもと、イギリスはこの数年で肥満政策を大きく転換してきた。2020年には政府が包括的な肥満戦略を公表し、「正しい情報を与えれば人は合理的に行動する」という前提の限界を明示した。2022年には、従業員250人以上の外食事業者に対するカロリー表示が義務化され、消費者が無意識に過剰摂取する環境の改変に着手した。
加えて、スーパーでは高脂肪・高糖分・高塩分(HFSS)食品の目立つ場所への陳列や、「1つ買うと1つ無料」といった多点購入を促すプロモーションが規制されている。子どもを対象としたジャンクフード広告についても、午後9時以前のテレビおよびオンライン広告が原則禁止された。これらはいずれも、「選択の自由」を狭める政策である。
しかし、イギリスが本気で問い直しているのは、「自由とは何か?」という点だ。
人間は生物学的に高カロリー食品を好む。安価で、手軽で、強く宣伝される食品に囲まれていれば、意志の力だけで抗うのは難しい。疲れているとき、忙しいとき、ストレスを感じているときほど、その傾向は強まる。問題は個人の弱さではなく、そうした選択を日常的に誘発する食環境そのものにある、というのがイギリスの結論である。
その結果、責任の重心は明確に産業側へと移りつつある。上院特別委員会の報告書は、過去30年にわたる肥満対策が失敗してきた理由として、「個人責任への過度な依存」と「ナニー・ステート批判への過剰な忌避」を挙げた。自主的な取り組みはほとんど成果を上げなかった一方、清涼飲料水への課徴金、いわゆる砂糖税は短期間で製品中の糖分削減を実現した。この事実は、企業行動が道徳ではなくインセンティブによって動くことを示している。
こうしてイギリスは、個人の選択や意志の力に期待することをやめ、政府が積極的に介入する方向へと舵を切った。健康的な選択を「努力目標」にするのではなく、「デフォルト」にするためである。この姿勢はしばしばナニー・ステート、すなわち過干渉国家だと批判される。しかし支持者は、これは自由の侵害ではなく、「健康を失わずに生きる自由」を守るためのパターナリズムだと位置づける。
太ったのは誰のせいか?
イギリスはこの問いを、個人の道徳や自己管理能力の問題としてではなく、制度設計と産業構造の問題として捉え始めている。自己責任から環境と産業の責任を問う社会へ、という思想転換は、日本の肥満対策、ひいては公衆衛生政策のあり方を考えるうえでも、無視できない示唆を含んでいる。
■
秋山 卓哉
食農倫理研究所 代表。食と農をめぐる価値対立や政策・産業の倫理を専門に研究。食にまつわる自由、環境倫理、動物倫理、公衆衛生、食文化、消費者選択を軸に国内外の動向を分析・発信。