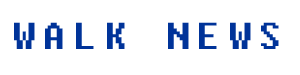2022年6月16日撮影。REUTERS/Florence Lo
[東京 30日] – 米国時間の1月23日、レートチェックを含む日米協調介入への思惑からドル/円 相場が大きく値を下げる場面があった。トランプ大統領がドル安を声高に支持するような発言をしたことも材料視されたようだ。その後、ベセント財務長官が介入の存在自体を否定し、「強いドル」への支持も表明しているため事態は落ち着いている。
<「米国も協力」というナラティブ>
もっとも、レートチェックの実施自体は否定されていないため、真相は闇の中である。「米国までも円安修正に本気」という真偽不明のナラティブ(物語)によって調整を強いられたドル/円相場は、その後も上値重く推移している。
歴史を振り返ってみれば、日米が同時期にレートチェックを実施したと思しき実例はなさそうであるため、これが常態化するようであればもう160円定着は難しくなるだろう。「相手がある話」の為替市場において、双方の利害が一致し、望む方向に向かって双方が策を講じればそれは100%実現する。その相手が基軸通貨国・米国であればなおさらだ。関係者以外は検証のしようがない最強のナラティブと言える。
<2024年との3つの違い>
政治的な実情は知る由もないため、あくまで推測の話をするしかないが、今回の1ドル160円前後という円安水準と、24年4-7月に直面した同じく160円前後という水準を比較すると、大きく分けて3点の違いがあるように思う。うち2点は円高が長続きしない材料、もう1点は円高を後押しする材料である。必殺とも言える「日米協調」の施策が存在するとして、いつまでドル/円相場を押し下げられるだろうか。簡単に検討してみたい。
24年と比較して最初の違いは、米連邦準備理事会(FRB)の金融政策姿勢だ。24年上半期を振り返ってみると、「Fedピボット(FRBの方向転換)」というフレーズに象徴される米金利の先安観が渦巻いていた。当時は「米国がドル安寄りの金融政策を講じているタイミングで日本が円高寄りの通貨政策を講じている」という状況にあり、円高・ドル安への反転は必然の帰結でもあった。しかし今回、FRBは利下げ終盤に差し掛かっており、トランプ政権でなければ利下げ局面自体が終わっている可能性すらあるくらいだ。こうした中、果たしてドル安・円高がどこまで加速するのか疑わしい。そもそも「ドル安でも大して円高にならなかった」というのが25年の経験であり、FRBが利下げの手を止め、米金利が底打ちするような事態に至った場合、円安となる可能性が高いと考えるのが自然だろう。
もうひとつが過熱感の違いだ。投機的なポジション動向の傾きは24年と現在でかなり異なる。為替介入は投機的に傾斜し過ぎたポジションを殲滅(せんめつ)するのに絶大な効果を発揮する政策だが、その「傾斜し過ぎたポジション」が今は果たして存在するのか疑わしい。
例えばIMM通貨先物取引における26年1月20日時点の円ポジションは約マイナス35億ドルのネットショートだが、24年4-7月は平均マイナス118億ドルのネットショートが構築されていた。当時はマイナス100億ドル規模のネットショートが常態化していた。また、後述するように、22-23年から引き継がれた莫大な貿易赤字もまだラグを伴いつつ残っていた。投機や実需が明確に円ショートに傾いた結果、160円という水準が実現していたが、そこまでの過熱感は今はない。
いわゆるセリング・クライマックスにあった24年と、日常風景として160円付近にある現在では人為的に仕掛けられる余地も限られてくるのではないか。そもそも今回の騒動はドルと円の間で起きたものだが、1月19日-26日の1週間における対ドルでの変化率を見ると、円の上昇幅が特別に大きいわけではなく、G10通貨では真ん中程度の反発でしかなかった。日米協調介入という必殺のナラティブでも円の反発は普通だったのである。
<貿易赤字は現在の方が小さい>
以上2点は円安地合いの強さを指摘する議論だが、もう1点は円高反転に期待を持たせる材料である。それは貿易赤字の規模が異なるという事実だ。
貿易収支が2年程度のラグを伴いつつ為替市場に影響を持つと仮定すれば(この点は諸説ある)、24年は22-23年の貿易赤字、26年現在は24-25年の貿易赤字が円相場に対して強い影響を持つことになる。もちろん、大まかな議論であり、22年のように超巨額の赤字が瞬発的に発生した場合、為替予約の範疇(はんちゅう)では手当てしきれず、即座にフローとして現れるものもあるはずだ。実際22年は過去最大の貿易赤字と円暴落が併存した。
貿易赤字と為替相場の対応関係を精緻に議論することはここでは控えるが、現在が当時と比較して「実需の円売り」の規模が統計上、だいぶ収束していることは大きな違いである。この点は円買い・ドル売り介入が効果を発揮しやすい環境と言える。
しかし、上述2点と総合した場合、少なくとも今回の騒動がワンショットで終わるならば、やはりドル/円相場は徐々に元の居場所に戻る可能性が高いと筆者は考えている。
<ナラティブの賞味期限>
もっとも、この話で最も重要なことは「米国までも円安修正に本気」という強力なナラティブの賞味期限をどこまで見積もるかだ。この際、本当に協調があったのかどうかは脇に置く。現実の介入がなくとも、レートチェックを含めた協調が考えられる可能性は今後も払拭できない。
その際問題になるのは、第2次トランプ政権が「円安是正(ドル高是正)」のための協調に長期的かつ誠実にどこまで付き合い続けるか、である。これまでの経緯を見ても明らかなように、米政権が何の対価もなく協力するとは考えにくい。円安是正によって米国に利があるからこその判断だろう。それが何なのかは本稿執筆時点では分からない。防衛費増額なのか、消費減税見送りなのか、日銀利上げ許容なのか――。いずれにせよ政治の話だ。
米経済諮問委員会(CEA)のミラン委員長を理論的支柱とするトランプ政権の発想に沿えば、とにもかくにも米国債の安定消化が優先事項である。1月に見られるような日本国債の超長期セクターの大崩れ(超長期金利の急騰)が続いた結果、日本国債の利回りは同年限の米国債に接近している。例えば30年債利回りはレートチェック騒動を経た現在で日本の3.6%程度に対し、米国は4.8%程度だ。騒動前、日本のそれは3.9%程度まで上昇していた。
こうした状況が続けば、米国債から日本国債へ乗り換えるフローも想定され、トランプ政権としては愉快ではない。かかる状況下、円安修正を契機に日本国債売りにも歯止めをかけたという考え方はあり得る。要は米国債市場の安定を念頭に協力したという趣旨だ。
だとすれば、である。実際の為替介入は(日本側の)米国債売りを要するオペレーションであるため、実行可能なオプションは今回のようなレートチェックを通じた脅しにとどまるように思える。現に、本稿執筆時点で為替介入は行われていないとベセント氏が明言済みである。
さらに言えば、トランプ政権にとってドル安が望ましいのかも疑義がある。ドル安でも輸出数量が押し上げられない米国経済の性質を踏まえれば、ドル安の直接的影響は相互関税も相まってインフレ圧力が輸入されることくらいではないのか。既に、対円以外では大幅なドル安が慢性化している中、さらにドル安誘導を図るメリットはあるのか。超長期ゾーンの米国債消化を間接的に手助けするという視点はあるが、継続的な協調を確約させるほどの材料なのか。もちろん、政治の世界の話ゆえ筆者には分からないが、賞味期限はさほど長くない可能性もある。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*唐鎌大輔氏は、みずほ銀行のチーフマーケット・エコノミスト。2004年慶應義塾大学経済学部卒業後、日本貿易振興機構(ジェトロ)入構。06年から日本経済研究センター、07年からは欧州委員会経済金融総局(ベルギー)に出向。08年10月より、みずほコーポレート銀行(現みずほ銀行)。欧州委員会出向時には、日本人唯一のエコノミストとしてEU経済見通しの作成などに携わった。著書に「弱い円の正体 仮面の黒字国・日本」(日経BP社、24年7月)、「『強い円』はどこへ行ったのか」(日経BP社、22年9月)など。新聞・TVなどメディア出演多数。note「唐鎌Labo」にて今、最も重要と考えるテーマを情報発信中。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab