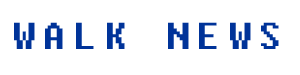トップニュース李忠謙コラム:トランプ氏によって、2025年の米国は私たちにとって見知らぬ姿になった
アメリカのトランプ大統領。(AP通信)
2025年も間もなく終わろうとしている。多くの若者がクリスマスや年越しを迎える準備を進め、新しい年に期待を寄せている。その一方で、年の瀬の台湾社会を震撼させる事件が起きた。3年前、飲酒運転を理由に空軍を除隊させられた元志願兵の張文が、ガソリン爆弾や煙幕弾、刃物を用いて台北の地下鉄駅とその周辺で大規模な無差別攻撃を行い、社会全体が悲しみと恐怖、怒りに包まれた。
張文は逃走中に転落死し、犯行の動機を示す言葉を何も残していない。この事件が、鄭捷事件以降で最大規模の無差別殺傷事件となった理由はいまだ解明されていない。単独犯なのか共犯がいたのかも不明なままだ。ネット上では犯人への怒りや死刑制度を巡る議論が噴出したが、それ以上に憂慮すべきは、事件に政治的立場を無理やり貼り付ける言説だった。「青い鳥だ」「草のような立場だ」「名前からして大陸配偶者の子ではないか」といった主張は少数派とはいえ、長いコメント欄の中で目を背けたくなる光景をつくり出していた。
政治的分極化や憎悪がネット空間で表出すること自体は、もはや驚くべきことではない。しかし台湾では、その分極化が憲法法廷にまで及び、法理に基づく議論よりも政治的立ち位置や宣伝が前面に出る状況が続いている。5人の大法官による自己正当化のもとで憲法法廷が再稼働したとはいえ、果たして今も「紛争を最終的に裁く最高機関」と言えるのだろうか。評議への出席を拒否した3人の大法官は、再開を支持する人々から見て、なお憲法とその価値を守る資格を持つのか──疑問は残る。
視線を国際情勢に転じると、「疑米論」や「反中論」といったレッテルが飛び交う中で、地政学の現実を冷静に見極めることは一層難しくなっている。米国在台協会(AIT)前処長の孫暁雅氏(サンドラ・オードカーク)は、健全な懐疑は民主主義に資するもので、単なる不信とは異なると述べてきた。しかし、この言論の自由を体現する考え方は、残念ながら台湾では主流になっていない。現実的な利害や法理よりも政治的立場が先行する状況は、2026年に向けて克服すべき大きな課題だ。
では、2025年の米国に対して、私たちは警戒心と疑念を強めるべきなのだろうか。残念ながら、多くの米国の専門家や研究者の見方を踏まえると、その答えは「イエス」に近い。トランプ政権が公表した2025年版「国家安全保障戦略」を見ると、米国は欧州の同盟国を競争相手とみなし、「退廃」「依存」「自由主義の過剰拡張」といった極めて厳しい言葉で欧州を批判している。台湾は民主と法治の先進地域を自任しているとはいえ欧州ではないが、専門家を驚かせたのは、この戦略文書がロシアと中国を「同格、あるいは友好国」と位置付けている点だった。
(関連記事:
中国軍「上海整備」説明の直後に青島で合流 福建艦と遼寧艦、二空母運用の演練か 第一列島線突破をにらむ
|
関連記事をもっと読む
)
その背景にあるのは、「米国を再び偉大に(MAGA)」という世界観だろう。MAGAは、西側内部で「文明の内戦」が起きており、とりわけ欧州では「文明の消滅」が進行していると捉える。支持者の目には、真の脅威はモスクワや北京の拡張主義ではなく、堕落した欧州同盟国の側にあると映っている。新たな国家安全保障戦略には、「有色人種が白人社会を静かに乗っ取っている」という暗い幻想すら見え隠れし、同盟関係を維持する前提として「白人社会」の存続が不可欠だという含意が読み取れる。
米誌『フォーリン・ポリシー』のコラムニスト、ハワード・W・フレンチ氏が指摘するように、この新戦略は、第二次世界大戦以降に共有されてきた「西側」という概念を解体しかねない。米国と欧州は、もはや同じ価値観や共通の利益を前提とする関係ではなくなりつつある。そうした中で、台湾は一体どこに立つべきなのか──その問いは、これまで以上に重く突きつけられている。
米中関係に焦点を戻すと、トランプ氏の対中政策は2025年に入り、意外な転換を見せている。『ニューヨーク・タイムズ』のホワイトハウス担当主任記者ピーター・ベイカーは、トランプ氏の中国政策こそが2025年最大の驚きの一つだと指摘する。かつてオバマ政権を「対中姿勢が弱腰だ」と批判していたトランプ氏が、今や「対中ハト派」に転じたからだ。実際、トランプ氏はバイデン政権が導入した多くの技術規制を撤回し、第1次政権時のように事あるごとに中国を非難する姿勢も後退させている。
シンガポールの元外相、楊栄文(ジョージ・ヨー)氏は『サウス・チャイナ・モーニング・ポスト』のインタビューで、トランプ氏が残りの任期で中国との関係安定を重視し、台湾を争点化することを極力避けようとしていると指摘した。そのため、日本の高市早苗首相による「台湾有事」論がトランプ氏から冷淡に扱われたのだという。楊氏はさらに、米中両国は互いに孫悟空の「金箍(きんこ)」をはめ合っているようなものだと例え、双方とも相手に「深刻な頭痛」を与え得る存在である以上、トランプ氏にとって中国との休戦が最も理性的な選択だと語った。
しかし、ワシントンのこうした現実路線は、アジアに新たなリスクをもたらす可能性もある。インド国家安全保障顧問委員会の元委員で、現在シンガポール国立大学の客員研究教授を務めるC・ラジャ・モハン氏は、トランプ氏が中国との経済関係維持を強調するあまり、商業的利益と安全保障上のコミットメントとの間で取引が行われるのではないかという懸念を招いていると警告する。アジアの同盟国により高い要求を突き付ける一方で、高市首相を事実上「切り捨てる」ような対応を取ったことで、米国がアジアにどのような見返りを提供するのかは極めて不透明になっている。
トランプ氏はノーベル平和賞を強く望んでいるとされるが、それは台湾海峡の平和(さらには台湾の独立)に資するのだろうか。ハーバード大学の国際政治学者スティーブン・M・ウォルトは、これはトランプ氏の自己顕示欲に過ぎないと見る。大々的に発表される和平合意の多くは、演出や見せかけに終わっているというのだ。ガザ和平案は、イスラエルによるヨルダン川西岸の緩慢な併合を覆い隠す「隠れみの」と評され、カンボジアとタイの国境紛争を終結させるとされた合意も、戦闘再燃によって米国の信頼を失墜させた。ルワンダとコンゴ民主共和国の停戦合意も、ルワンダが支援するM23武装勢力によって短期間で破られた。
ウォルトは、トランプ氏の和平努力が失敗に終わる理由として、短気さ、細部への無関心、娘婿のジャレッド・クシュナーのような「素人外交官」への依存、そして一方にのみ有利な解決策を押し付けがちな姿勢を挙げる。最大の皮肉は、トランプ氏が大規模戦争を警戒しているように見えながら、その行動は本格的な外交調停というより、「広報活動や自己誇示」に近い点だ。動機の中心は、ノーベル平和賞獲得にある可能性が高い。結果として生まれるのは、紛争の根本原因に手を付けない象徴的合意であり、その一方で、より深いレベルでの価値観の変化が米国の同盟体制を蝕んでいる。
欧州を遠ざけ、中国と和解し、演出過剰な和平合意を打ち出す――これらは孤立した出来事ではなく、いずれもトランプ氏のMAGA世界観の異なる側面にすぎない。そしてそれらは、従来の敵味方の境界が曖昧になり、国際秩序の基盤が次々と引き抜かれていく暗い将来像を浮かび上がらせる。「米国第一」という教条の下で地政学の構造プレートが大きく動く中、「米国を疑ってはいけない」「米国への不信は許されない」といった立場を最初から前提にする考え方は、本当に、2026年に大きく変わろうとする世界情勢に台湾が向き合うための“出発点”になり得るのだろうか。さらに難しいのは、「中国を疑ってはいけない」「中国への警戒も口にすべきではない」という姿勢も、決して答えにはならないという点だ。政治的立場が先行し、分極化が進む台湾社会において、私たちは腰を据えて対話し、現実的な道筋を見いだすだけの忍耐と知恵を持ち得るのだろうか。
2026年、私たちにその幸運があることを願うばかりだ。
更多新聞請搜尋🔍風傳媒
タグで探すおすすめ記事