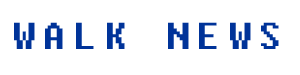羽田空港から飛行機で3時間。那覇空港の外に出ると、強い日差しと激しい太陽雨(沖縄の言葉でティーダアミ)に迎えられた。蒸した空気と雨に包まれながら、体にまとわりつく湿気と雨量に驚いていると、15分も経たずに雨は止んだ。東京とは全く違う気候に、はるか遠くへ来たことを実感した。
ここはかつて、独立した琉球王国として大きく栄えた地。1609年、薩摩藩の侵攻によって日本の影響下に置かれたものの、中国とも交易・交流を続けていた。しかし1879年、明治政府が武力と政治的圧力をもって王国を強制的に併合。一連の政策は「琉球処分」と呼ばれ、沖縄県として日本に編入されただけでなく、方言札の導入などの同化政策によって、文化や誇りまでも奪われた。1945年、本土を守ることを優先した日本軍の戦略によって米軍が沖縄に上陸、と激しい地上戦が繰り広げられ、20万人超が犠牲となった。そのうち約10万人は民間人だった。その後、27年にわたる米軍統治のなかで基地は拡大し、1972年の本土復帰後も、その影響は色濃く残り続けている。
「政治や基地のことはあまり沖縄の人と話さない」
那覇市内から北上した先、宜野湾市の中央に位置するのが普天間基地だ。その周囲には住宅や学校、市民の生活が密接に隣接している。それもそのはず、普天間基地のある場所は、戦前には約9,000人が10の集落に分かれて暮らしていた豊かな地域だった。豊富な湧水と美しい景観から「神山」とも呼ばれたこの地は、戦後、住民が収容されている間に米軍が鉄条網で囲い込み、強制的に接収した。先祖の墓が基地内に残っている人もおり、近隣の保育園には米軍機の部品が落下する事故も起きている。
基地のそばにある飲食店に入ると、店主が「シークワーサーあげるよ、水に絞って飲んでみて」と声をかけてくれた。話すうちに、彼が宜野湾市で生まれ育ち、数年東京に住んだのち故郷へ戻ってきたことがわかった。「米軍が来てよかったことといえば、本土より先にトイレが水洗になったことくらいだね。ここは普天間飛行場に近いし、事故も多くて危ないよ」と、皮肉を交えつつも柔らかな表情で話してくれる。20分ほどの会話の最後に、彼はこうも言った。「でも、政治のこととか基地の話は、あまり沖縄の人とはしないよ。ここにはお客さんも来るし、周りには米兵も住んでるしね」。米軍基地があるということは、米兵やその家族、基地内で働く人々とともに暮らすということ──その現実を突きつけられた瞬間だった。